6-3 ロジャー・ニコルズと小さな友達の輪
ロックと自作自演
《ロック》の定義とは一体なんなのか。僕も未だにはっきりとは答えを出せてはいないんだけど、ファッションや精神論的な話ではなく音楽ジャンルとしてはっきり定めたいなぁと思っている(あくまで自分の中でね)。とはいえ精神論的な目線が僕の中に全くないかと言えばそういうわけでもなくて。
よく《反抗(カウンター)》こそが《ロック》である、と言われる。まさに60年代末のヒッピームーブメントや70年代半ばのパンクムーブメントは《反抗》そのものであるし、この二つは《ロックファッション》としても一般的にイメージが強い。確かにロックは既存の何かに反抗し続けることで受け継がれていったと言えるだろう。ただ僕はもっと大まかで単純で最低限の精神論をずっと持っていて、それは《自己表現》こそが《ロック》であるということだ。これは定義でもなんでもなくて大前提のことだけどね。
そんなのロックに限らず芸術全般そうじゃんって言われるかもしれないが、まさにその通りで、言い換えればロックは芸術であるべきだと思っている。そんなわけでより芸術的であり、より自己の内面の深いところを表現したといえる、サイケデリックロック、アートロック、プログレッシブロックあたり、即ち60年後半から70年前半あたりをロックのど真ん中と僕は位置付けているわけだ。
さて、そんな風にロックに熱中しはじめて間も無く《自己表現》が《ロック》であると超大まかな精神論を打ち出した僕にとって、重要になる、というか気にしてやまないのがそのバンドが《自作自演》であるかどうかであった。作詞作曲をバンドメンバーがしているのか、しているなら誰がしているのか、僕の好きな曲は誰の世界を表現したものであるのか、それは僕にとってかなり重要なことであった。こういう自作自演、作詞作曲を気にする傾向は特に日本人に多いって話を聞いたことがある。欧米の人は「誰が作ったとしてもいい曲なのは変わりないじゃない」って感覚なんだろうか、なんかその方が正しそうだし理解はできるけどやはりどうしても僕は気になる。
そんなわけで僕にとってのロックアイドルはいつも作曲家で表現者であったわけだ。ギターヒーローや名プレイヤーにあまり興味がなく、曲構成の縛りの強いブルースに疎いのもそんな理由からだろう。
そんなロックキッズだった僕はほぼ同時期に2つのジャンルにハマることになる。それが前章で熱くなっていた《ブリティッシュフォーク》と今回の《ソフトロック》である。
この2つは僕がインターネットを使い出してからの劇的な情報革命がもたらした最高の音楽達であるが、この2つが《自作自演》を根底に持っていないジャンルとも言えるものなんだな。
アメリカンフォークは《自作自演》の象徴ともいえるが、ブリティッシュフォークは伝承歌、トラディショナルソングを強く重んじるジャンルであるし、ソフトロックはプロの作曲家やアレンジャー、プロデューサーが活躍を見せるジャンルである。
この《自作自演》が主体ではない2つのジャンルを《ロック》に含めるかはどうかは正直難しいところで、今回見ていくソフトロックなんかはかなり《ポップス》に近いところにあるんだろうけど…
僕は常にロック好きという立ち振る舞いをしてきた。ロックが音楽的に幼稚であると軽視される傾向にあることを自覚しても尚。尊厳を守るために「ロックと言っても僕が好きなのは…」とブライアンウィルソンがバッハの域まで到達したことやピンクフロイドの絵画的とも言える表現力の極みを説明することは可能であるが、なるべく「ロックが好きだ」とのみ言うようにしている。「ロックと言っても…」という発言は自らロックを幼稚だと認めてしまっている気がするからだ。「ロックと言っても60年代後半〜70年代前半は芸術的で表現豊かなんだよ」ではなく、「ロックは芸術的で表現豊かだ!好きだ!」と言いたいのだ。僕の尊厳ではなくロックの尊厳を守るために!
で、そんなロック好きな僕が《ブリティッシュフォーク》と《ソフトロック》に強く惹かれてるんだから、「《自作自演》が《ロック》の大前提だ!」という自論から外れはするが、《ブリティッシュフォーク》と《ソフトロック》は《ロック》に含まれるのだということにさせてもらう(何言ってんだか)。ま、《ロック》に含まれないにせよロック史を語る上で避けては通れないので行かせていただきます。
6-3 ロジャー・ニコルズと小さな友達の輪

『フリッパーズギターやピチカートファイブら日本の《渋谷系》は《ソフトロック》が元ネタであることを公言し、その存在を世に広めた。』
このことは6章の初めに書いたが、正直なところ渋谷系の音楽性は"ソフトロックの影響"というより9割このロジャー・ニコルズ及びRoger Nichols&The Small Circle Of Friendsの影響下にあると言えると思う。
ロジャーニコルズ(通称ロジャニコ)は作曲家としての活躍がより有名であり、"ロジャニコ作曲&ポール・ウィリアムス作詞"という名コンビで70年代初頭にカーペンターズやスリー・ドッグ・ナイトらにヒット曲を提供した。
バート・バカラック&ハル・デヴィッド、キャロル・キング&ジェリー・ゴフィンといったアメリカンポップスの名コンビに負けないくらい重要な作詞作曲コンビの片割れであるロジャニコであるが、彼も元々は《自作自演》のミュージシャンであった。
作曲家としてはかなりの有名人であったが、その音楽キャリアをスタートさせたバンド、Roger Nichols&The Small Circle Of Friendsについてはあまり認知されてなく、それが遥か遠くの島国日本で《渋谷系》の偉人達のおかげで《ソフトロック》として再評価され、唯一作であった68年1stアルバムが87年にCD化されたわけだ。アメリカより日本で先にCD化されてるんだからすごいよね。これはロック史において日本が誇れる数少ない偉業であるだろう(発掘が数少ない偉業ってのも悲しいけど)。
Roger Nichols&The Small Circle Of Friends

マレイ・マクリオード、メリンダ・マクリオードの兄妹とロジャニコの3人組のフォークボーカルグループは当初"ロジャーニコルズトリオ"という名前でカリフォルニアを中心に活動しており65年頃にA&Mレコードと契約する。
そして"Roger Nichols&The Small Circle Of Friends"と名前を改めて68年にようやく1stアルバム「Roger Nichols&The Small Circle Of Friends」をリリース。
ヴァイオリンのピチカート奏法から始まるロジャニコワールド全開のDon't Take Your Timeで幕を開けるこのアルバムはミレニウムの「Begin」と共にソフトロックの金字塔と絶賛されている名盤であるが全12曲の内半分がカバー曲である。
ビートルズが2曲、ラヴィン・スプーンフルが2曲、バート・バカラック&ハル・デヴィッドの作品とキャロル・キング&ジェリー・ゴフィンの作品が1曲ずつの計6曲がカバーであるが全てが柔らかく優しい《ソフトロック/サンシャインポップ》に仕上がっている。特にビートルズのI'll be backのアレンジは凄まじいものがある。アレンジャーにはニック・デカロ、ボブ・トンプソン、マーティ・ペイチ、モート・ガーソンの4人の名前がクレジットされている。
さてオリジナル6曲だが、内4曲の作詞をトニーアッシャーが担当。トニーアッシャーは前回紹介したビーチボーイズの66年名盤「ペットサウンズ」に参加した作詞家である。

このトニーアッシャー、作詞家でコピーライターであるようなんだけど「ペットサウンズ」でwoudn't it be niceやgod only knowsといった歴史的名曲の詞を書いたことでとにかく有名で、他の情報はよくわからない。そんなに幅広く活動していた作詞家ではないようで、ロジャニコも間違いなく「ペットサウンズ」での仕事ぶりを見て作詞を任せたのであろう。
ロジャニコのキュートで浮遊感溢れるオリジナル曲はほんとうに素晴らしい。転調が多いのも特徴であるが、ポップセンスが光り過ぎて全く聞きにくくない。コーラスワークについてはブライアンウィルソンやカートベッチャーのほうがよく取り上げられるがロジャニコの3人のコーラスもすごいのよね。変なとこいくというか。まさに《渋谷系》そのものなのが6曲目のLove So Fineで、ピチカートファイブにこんなに同じでいいのか、っていうくらい丸パクリの曲があるくらいで。曲はほとんどが3分未満の長さであり、このコンパクトさはソフトロックの特徴でもある。
ソフトロックの代表作でありながらこのアルバムみたいな他のソフトロックって実はなくて、独特なんだよな。気持ちいい。
オリジナル曲6曲の内2曲がメンバーのマレイ・マクリオードが並行して活動していたThe Paradeというバンドが関わっていて、このバンドも素晴らしきソフトロック/サンシャインポップである。


このパレードも3人組であり、67年のシングル「Sunshine Girl」は割とヒットしたようである。キーボードのジェリー・リオペルはフィル・スペクターのフィルズレコードで仕事をしていた人物であるよう。レッキングクルーではないのかな…?
さぁロジャニコ、今となれば特に日本では名盤中の名盤であるが当時は全く話題にならずスモールサークルオブフレンズは解散。ロジャニコはその作曲能力を買われA&Mレコードに職業作曲家として契約することになる。
ロジャー・ニコルズとポール・ウィリアムス

A&Mは作詞家ポール・ウィリアムスと作曲家ロジャニコというコンビを組ませた。ロジャニコは学生時代バスケでかなりの成績を残したらしく巨人であり、ポールウィリアムスは小柄な男だ。この凸凹コンビが作った曲を70年にカーペンターズがヒットさせ、人気作曲家の仲間入りとなるんだが、その前、68年69年に作ったいくつかの曲と提供したバンドがソフトロックと呼べるものである。少しだが把握している分だけ。
クロディーヌ・ロンジェ

フランス出身の女性ポップ歌手であるが、カリフォルニアに移り住みA&Mからデビューしていることからフレンチポップではなくソフトロック/サンシャインポップとして再評価されたクロディーヌ・ロンジェ。
表現豊かで可愛らしい彼女の歌声だが幻想的な雰囲気を持っていてソフトロックと呼べる音楽に仕上がっている。特に68年3rd「Love is blue」がソフトロックど真ん中!
このアルバムの最後の曲It's hard to say good byeがロジャニコ&ポールウィリアムスの曲である。
Harpers Bizarre

67年にサイモン&ガーファンクルの59番街橋の歌のカバーでワーナー・ブラザース・レコードからデビューしたソフトロック/サンシャインポップバンド、ハーパース・ビザール。
ワーナーの名プロデューサーレニー・ワロンカーがプロデュースを務め、ワロンカーの親友であるランディ・ニューマン、ワーナーに入社したばかりのヴァン・ダイク・パークス(ビーチボーイズ「スマイル」作詞)らが関わっている。このレニーワロンカー周辺のアレンジャーやスタジオミュージシャンが作り出す音楽はワーナーの所在地から《バーバンク・サウンド》と呼ばれることとなるが、この60年代後半の頃の《バーバンク・サウンド》はほぼほぼソフトロックと呼べるものである。
そんなハーパース・ビザールに68年にロジャニコ&ポールウィリアムスがThe Drifterという曲を提供している。
これが本当に名曲で、ロジャニコはスモールサークルオブフレンズでビートルズのWith a little help from my friendsをカバーしてるんだけど、それをよりソフトによりポップにしたのがこのThe Drifterって感じ。ハーパース・ビザールの歌も見事にマッチしていて最高です。この曲が収録されている68年3rd「The Secret Life of Harpers Bizarre」は《サージェント症候群》の香りも漂う名盤。
Peppermint Trolley Company

ロジャニコは68年にハーパース・ビザールに提供したThe Drifterを69年にRoger Nichols&The Small Circle Of Friends名義でセルフカバーしてシングルリリースしている。そのシングルのB面の曲がTrustという曲で、こちらもセルフカバー。初出はPeppermint Trolley Companyというバンドに提供したものである。
Peppermint Trolley Companyはソフトロック界隈では、特にロジャニコ界隈では珍しくバンド色が強いサウンドで、サイケ色も見え隠れするロックバンドである。
Trustを収録した68年唯一作「Beautiful Sun」はソフトロックファンにもサイケファンにも響く傑作。
バンドは70年代にBonesと名を改めて2枚アルバムをリリースしているようだがこちらは未聴。聞かねば。
The Monkees

今やセブイレのテーマソングになってしまっているDaydream Believerの原曲を歌ったモンキーズは、僕の中で《自作自演》じゃないバンドの代表である。ビートルズのようなバンドをアメリカでも作ろうというTV番組で作られたバンドであり、僕は「ビートルズになりたかったら自分で曲書かなきゃ。ロックじゃねぇ!」と長らく無視していたんだけど。
しかしこの「目指せビートルズ」なプロジェクトのためにアメリカの選りすぐりの作曲家が曲を書き、演奏はレッキングクルーの面々、であるので楽曲は素晴らしいものが多いんだな。
69年にシングルのB面として収録されたSomeday Manがロジャニコ&ポールウィリアムス作曲で抜群のソフトロックである。ロジャニコ得意の転調が炸裂、モンキーズのデイヴィ・ジョーンズの声も見事にマッチしている。
69年の7th「Instant Replay」がCD化された際に追加されたボーナストラックでSomeday Manを聞くことができる。この頃になるとようやくモンキーズのオリジナルも増え始めていて、後にカントリーロックのパイオニアと呼ばれることとなるマイク・ネスミスもその片鱗を見せている。そんなこともあってアルバム全体はソフトロックと呼べるものではないが、モンキーズを見直したアルバムとしてお気に入りのアルバム。
カーペンターズ

ロジャニコ&ポールウィリアムスは国民的人気バンドであったモンキーズに名曲Someday Manを書いたわけなんだけど、69年の頃は最早モンキーズブームは終わっており、やはり2人の作曲家としての成功はカーペンターズとの出会いであるだろう。
ロジャニコが作ったカリフォルニアの銀行のCMソング(30秒くらいのものだろうか)をリチャード・カーペンターが気に入り「これのフルバージョンはないのか?」と要請があり作り上げ70年に提供したWe've Only Just Begun(愛のプレリュード)が大ヒット。 同70年にはスリードッグナイトにもOut in the Countryを提供し、人気作曲家の仲間入りを果たす。その後カーペンターズの代表曲であるRainy Days And Mondays(雨の日と月曜日は)や Let Me Be the One(あなたの影になりたい)、I Won't Last A Day Without You(愛は夢の中に)を提供し栄光を手にする。
カーペンターズもソフトロックに数えられる場合もあるようだが、やはり僕の中でカーペンターズはピアノ中心のポップスでありソフトロックとは言えないかな。やはりバロックポップ的な要素がソフトロックには必要なんだよな。カーペンターズはもちろんめちゃくちゃ素晴らしいけどね。
なわけで68年〜69年のスモールサークルオブフレンズと提供作品がロジャニコのソフトロックにあたるのかな。そう考えるとソフトロックの時期は60年後半〜70年前半と書いたけど、70年以降はあんまりないのかも…
ポール・ウィリアムスのデビューとコンビ解消

70年に2人はROGER NICHOLS & PAUL WILLIAMS名義で「WE'VE ONLY JUST BEGUN」というアルバムをリリース(見たことない、このアルバム)。
カーペンターズに提供したタイトル曲、ハーパースビザールのThe DrifterやモンキーズのSomeday Manなどのセルフカバーを中心に70年までの2人の集大成とも言えるアルバムである。
同70年にポールウィリアムスはアルバム「Someday Man」でソロデビュー。
この後シンガー、さらに俳優としても活躍し忙しくなりロジャニコとの関係も悪化、72年に2人の作詞作曲コンビは解消となる。
ポールウィリアムスは活躍を続けるが、ロジャニコは音楽業界から姿を消してしまう。
スモールサークルオブフレンズ再結成

その後ロジャニコが世間に姿を見せるのは95年になってからで、Roger Nichols and a Circle of Friends(Smallが抜けてる)名義で「Be Gentle With My Heart」をリリース。これは渋谷系による日本でのロジャニコブームが彼を動かしたものである。これは名義も違うし、ロジャニコのソロとして扱うべきアルバムだろう。
そして2007年にRoger Nichols and The Small Circle of Friends(Small有り!)で実に39年ぶりの2ndアルバム「Full Circle」がリリースされた。こちらはマクリオード兄妹も参加し、正真正銘のスモールサークルオブフレンズの2ndアルバムだということで日本のソフトロックファンを喜ばした。やはりThe Drifterやカーペンターズ関連のセルフカバーが目立つが書き下ろしも何曲かあり、相変わらずなロジャニコのポップセンスに大満足。
2012年には3rd「My heart is home」をリリースしてるが、こちらはまだしっかりは聞けていないが軽く聞いた感じ「あれ…思ってたのと違う」って印象。
まとめ
ロジャニコ、こんな感じです。曖昧な表現になるけど〝良い曲〟を聴きたいなぁって時はロジャニコの曲聴いとけば満たされます。
まず68年スモールサークルオブフレンズは必聴!気に入ったらパレードも!
不思議系女性ボーカルが好きならクロディーヌ・ロンジェはオススメ!
《サージェント症候群》好きならハーパース・ビザールも!
ペパーミント・トローリー・カンパニーはサイケロック好きにも!
僕と同じくモンキーズを軽視してるなら60年代後半のブームを終えた後のモンキーズも!
図を繋いどきます!

では次回はコーラスの魔術師カート・ベッチャー!


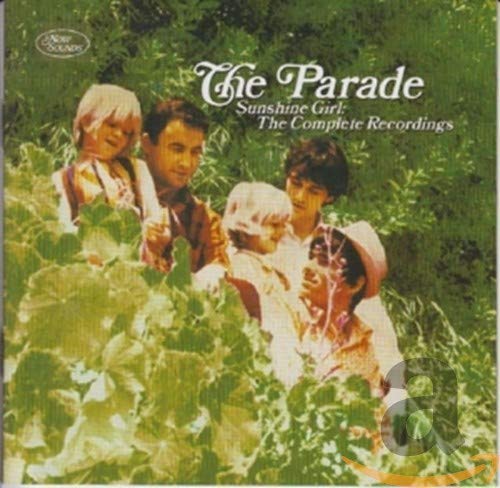
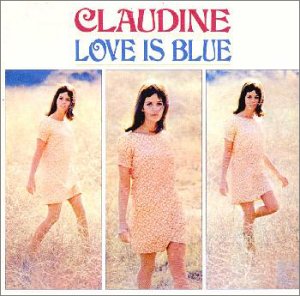

![The Peppermint Trolley Company [Analog] The Peppermint Trolley Company [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xaGl+O9GL._SL500_.jpg)


![Someday Man [Analog] Someday Man [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/51QGdl31GVL._SL500_.jpg)


