6-11 うわさの男、ハリー・ニルソン①(第96話)
1960年代に誕生したアメリカンロックにおける《グレート・アメリカン・ソングブック(1920年〜50年代のアメリカ流行歌やジャズ・スタンダード)》の影響は如何に。
文化というのは常々メインカルチャーとサブカルチャーのシーソーゲームだ。20世紀前半の古き良きアメリカンポピュラーミュージック《グレート・アメリカン・ソングブック》の時代を終わらせたのは1950年代後半に登場したロックンロールだった。ブルースやR&Bといった黒人音楽をルーツに持つロックンロールは保守的な大人達から非難を浴び、エルヴィス・プレスリーの徴兵、バディ・ホリー、リッチー・ヴァレンスやエディ・コクランの死などの不幸も重なり2,3年という短期間でブームは終わる。次のトレンドは保守的な大人も気にいる毒気のないポップシンガーやガールグループ、そしてフォーク・リヴァイバル勢だった。それらを蹴散らしたのが60年代半ばブリティッシュロックの侵攻(ブリティッシュ・インヴェイジョン)でありその煽りを受けてアメリカン・ロックが誕生した。
こうして入れ替わり立ち替わるメインカルチャーとサブカルチャーだが、ただカウンターを喰らわすだけに留まらず常に互いに影響を与え合い文化を育てていく。フォークリヴァイバルはブリティッシュインヴェイジョンと結びつきフォークロックを誕生させたし、フィル・スペクターのサウンドはロックに緻密さを与えた。未来と過去には必ず因果がある。それが歴史でそれが時間というものだ。
60年代末、主にロサンゼルスで作られた《ソフトロック》はアメリカンポップの要素が強いがブリティッシュインヴェイジョンの影響も多分にある特殊なものだった。そのどっちつかずなスタンスが当時流行らなかった要因かもしれないが、〝保守的〟〝古臭い〟と若者から敬遠されていた《グレート・アメリカン・ソングブック》や新トレンドのフォークロックにサイケデリックロック、さらにはカリプソやボサノヴァなどの中南米音楽を混ぜ込んだポップソングはイギリスにはないアメリカ独特のサウンドを持っている。《ソフトロック》は大抵ストリングスやホーン楽器等によって装飾されていることから《バロックポップ》を含む音楽性とされているが、《グレート・アメリカン・ソングブック》は別名《America's classical music(アメリカのクラシック音楽)》と呼ばれるようにストリングスやホーン楽器を駆使したジャズ・スタンダードや映画音楽であり、《ソフトロック》のアレンジはヨーロッパのバロック由来というよりも《グレート・アメリカン・ソングブック》由来という方が正しいのかもしれない。そういう視点で聴いてみるとビーチボーイズの「ペットサウンズ」はバロックポップというよりも《アメリカン・クラシック・ポップ》なのではないかと思うのだ。いや厳密にはどちらの影響も、というかどちらの研究もしているのだろう。そもそも《グレート・アメリカン・ソングブック》にはもちろんヨーロッパのクラシック音楽の影響があるわけだし。
ソフトロック勢の中でも一際《グレート・アメリカン・ソングブック》に接近したのがワーナー・ブラザーズ・レコードのレニー・ワロンカーの元作られた〈バーバンク・サウンド〉だろう。その古臭さと当時の最先端技術が同居した独特なサウンドを作り出したのはヴァン・ダイク・パークスとランディ・ニューマンだ。彼らはハーパース・ビザールやワーナー移籍後のボー・ブラメルズ等のビートルズライクな楽曲に《グレート・アメリカン・ソングブック》をモチーフにしたアレンジを施し唯一無二のサウンドを作り出したが、自身のソロではより《グレート・アメリカン・ソングブック》に接近した作品を作り上げた(のでソフトロックとは呼べないものに)。
そしてもう1人、ヴァン・ダイク・パークスとランディ・ニューマンと同世代で関わり合いもあり同じ志を持った男がいた。71年に〝Without You〟で奇跡の歌声を持った歌手としてスターとなるハリー・ニルソンも60年代末は素晴らしき《アメリカン・クラシック・ポップ》を作り出していたのだ。
6-11 うわさの男、ハリー・ニルソン①(第96話)

皆さんにとってハリー・ニルソンとはどんな男だろうか。カバー曲がヒットし、自身の曲はヒットしない、そんな男だろうか。ソングライターとしてヒット曲を多数提供しており、自身でも素晴らしい曲を作り歌っているのに、歌がうますぎる故に歌手として評価されすぎてSSWとしての姿は一般的に知られていない、不幸な男だ。
ニルソンとの出会い
かくいう僕も出会いはやはり〝Without You〟だった。誰しも子供の頃から自然と聴いている“家のCD”というものがあるだろう(厳密には親のCDか)。僕の家ではビートルズの「1」だったり、イーグルスやジャクソン・ブラウンだったりシンディ・ローパーだったりダイアー・ストレイツだったりしたわけだが、そんな“家のCD”の中に一枚「Kiss」という70's〜90's頃の洋楽ヒットラブソングをまとめたオムニバスアルバムがあった。
ホイットニー・ヒューストンの〝All At Once〟、Az Yetの〝Hard to Say I'm Sorry(シカゴの。ピーター・セテラも参加してる)〟、エア・サプライの〝Lost In Love〟、バングルスの〝Eternal Flame〟、J.D.サウザーの〝You're Only Lonely〟、そしてニルソンの〝Without You〟など至極の超ヒットラブソングが収録されたオムニバスアルバム。これが割とお気に入りでよく聴いていて、中学くらいの時自分用にブックオフで購入したほどで、僕の洋楽ポップソングのランドマークとなっている。久しぶりに聴いたら何だか堪らない気分になった。
そんなわけで後にロックにハマり、60'sにハマり、そっちの経路でニルソンと再会するまではしばらくの間ニルソンをポップシンガーだと思っていたし、〝Without You〟がバッド・フィンガーのカバーだなんてことも知る由もなかったわけで。
ニルソンの全盛期(チャート的に)は〝Without You〟が収録された71年「ニルソン・シュミルソン」辺りであるが、彼のキャリアは大きく3つに分けることができる。緻密なスタジオワークによって《グレート・アメリカン・ソングブック》的古き良きアメリカなアレンジとビートルズ的ポップロックを融合させた60年代後半、世界的ヒットとなった「ニルソン・シュミルソン」から始まる70年代前半の〈シュミルソン3部作〉、酔いどれながらもジョン・レノン やリンゴ・スター、ヴァン・ダイク・パークスらとの興味深いコラボレーションを魅せた70年代半ば、どれも面白いがやはりここでは《ソフトロック》的要素も大きく含んだ60年代のニルソンを主に見ていこうかと。まずは軽いバイオグラフィーから。
ニルソンのバイオグラフィー
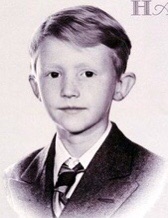
1941年ニューヨーク、ブルックリンにハリー・エドワード・ニルソン3世は誕生。3歳の時に父親が家族を捨て、母と妹と共にニルソンはロサンゼルスへ移住。家計を支えるために若い頃からパラマウント・シアターの座席案内の職に就いていたが、60年に劇場が閉鎖されると銀行の夜勤の仕事に就くようになる。
音楽の方はサーカス団員であった祖父母の影響やニルソンに歌の教育を施した叔父の影響もあってか、58年までにエヴァリー・ブラザーズスタイルのハーモニーデュオで歌い、ギターとピアノを学び、ミュージシャンを志すようになる。
銀行員として働きながら音楽の鍛錬を続けていた62年、某音楽出版社に売り込みに出向いた際にセッションギタリストのスコット・ターナーに歌を気に入られ、ターナーが作曲したデモに1曲5ドルのギャラで歌を吹き込む。この時の音源は77年に「Early Tymes」として日の目を浴びることになるが、リリースの際ターナーが改めてニルソンに正式なギャラの支払いを持ちかけるとニルソンは「もう貰った(1曲5ドル)」と答えたという粋な逸話がある。
このターナーとのセッションで出会ったジョン・マラスカルコという作曲家と共に仕事をするようになり64年にシングルを数枚リリースする(Bo Pete、Johnny Niles、Foto-Fi Fourといった様々な名義で)。ジョン・マラスカルコはリトル・リチャードの楽曲を作っていたことで知られる人物である。
変名ではあるがデビューを飾ったニルソンはまずはソングライターとして評価されていくことになる。64年にフィルスペクター作品に3曲貢献(ロネッツが2曲、モダン・フォーク・カルテットが1曲歌った)し、67年にはモンキーズが〝Cuddly Toy〟を、ヤードバーズが〝Ten Little Indians(ラストのジミー・ペイジのギターは衝撃的!)〟をグレン・キャンベルが〝Without Her〟を取り上げた。自身の活動としてはハリー・ニルソン名義でキャピトル傘下の〈タワーレコーズ〉からシングル4枚とデビューアルバム「Spotlight on Nilsson」を64〜66年の間にリリースするが大して話題にならず、SSWハリー・ニルソンの名が世に轟くのはこの後67年に〈RCA〉と契約してからである。ちなみにこの時点でまだ銀行の仕事を続けており、RCAに移籍してからやっと音楽一本でやって行く決意に至る。
変名で数枚シングルリリースしたり、〈タワーレコード〉での話題にならないシングルとデビューアルバムをリリースした辺りはデヴィッド・ボウイの下積み時代と被るところがある。現にボウイ同様この後の2ndが事実上の1stと呼ばれることが多く、ニルソンの真のキャリアスタートとされている。
67年2nd「Pandemonium Shadow Show」
とはいえこのアルバムも世間的にはさほど話題にならなかった。が、ニルソンの持ち味はこのアルバムですでにほとんど発揮されている。歌を1人で多重録音していく“宅録の走り”とも言えるスタイル、いくつもの声色を使い分けるカメレオンボイス、ルイ・アームストロングゆずりの自由奔放なスキャット、優れたソングライティングセンス、そしてバロックポップともアメリカンクラシカルとも取れる緻密なアレンジ。ライブを行わずスタジオワークに固執した点もこの時代ならではのスタイルだ。
ヤードバーズ、モンキーズ、グレン・キャンベルに提供した〝Ten Little Indians〟、〝Cuddly Toy〟、〝Without Her〟、家族を捨てた父について歌った〝1941〟など素晴らしいオリジナルソングが並ぶが、やはりまず目立つのはカバー曲とそこで魅せる歌唱力だろう。ビートルズの〝You Can't Do That〟、〝She's Leaving Home〟、フィルスペクター作の〝River Deep – Mountain High〟などアルバムの約半数がカバー曲であるが、特筆すべきは〝You Can't Do That〟。言わずと知れたザ・ビートルズ64年「A Hard Day's Night」収録ジョン・レノン作の名曲だが、ニルソンはこの曲を軸にしつつバッキングコーラスに他のビートルズ楽曲17曲のフレーズを変わる変わる差し込むという斬新なカバーアレンジを展開した(ドライヴマイカー、ハードデイズナイト、ペーパーバックライター、グッドデイサンシャイン、レディマドンナ、ストロベリーフィールズなどなど)。これはもはやマッシュアップであり、非常に現代的な、デジタル時代的なアイデアである。ビートルズカバーとしてはCyrkleの〝I'm Happy Just To Dance With You〟以上の衝撃で、ビートルズへの愛の深さはバークレイ・ジェイムス・ハーヴェストの「Titles(ビートルズの曲名だけで歌詞を作った曲)」に匹敵する。この〝You Can't Do That〟がニルソン初のチャートインシングルとなり(米122位,カナダ10位)、後に定着していく〈カバー曲のみヒットするニルソン〉というイメージの始まりとなった。
アルバム自体は世間的には話題にならなかったが、68年ビートルズによるアップル・コア設立の際LAからロンドンへ飛んだデレク・テイラーがビートルズにこのアルバムを聴かせると、ジョンはニルソンに直接電話をかけ絶賛し、ジョン、ポール両名がインタビューで好きなアメリカのアーティストとしてニルソンの名を挙げたという話は有名。アップル・レコードに移籍するという噂やジョン、リンゴ、ジョージと交友を深めた70年代にはポールの代わりにニルソンでビートルズが再結成するという噂なんてのも流れ、数々存在する〈5人目のビートルズ〉の1人に数えられることとなる。
ジョージ・ティプトン

さて、『グレート・アメリカンソング・ブックとソフトロックの関係』というテーマから書き出したハリー・ニルソンだが、実のところ60's後半のニルソンのバロックやアメリカンクラシカルな側面はアレンジャーのジョージ・ティプトンの存在が大きい。タワーレコーズ時代を含めて64年〜71年までニルソンのアレンジャーとして大きく貢献した男であり、他にもサンシャイン・カンパニーなどのアレンジを手掛けたことで知られる。ニルソンも〈シュミルソン3部作〉のラスト73年「夜のシュミルソン」でフランク・シナトラのアレンジャーだったことで有名なゴードン・ジェンキンスを起用し《グレート・アメリカン・ソングブック》のカバーアルバムを作るなどもちろん古いアメリカポピュラー音楽に対する造詣は深いが、60年代末にバーバンクサウンドに匹敵する作品を残せたのはジョージ・ティプトンあってこそだろう。
このニルソンとジョージ・ティプトンの名コンビが最も上手く機能したと思われるのが次作68年3rd「Aerial Ballet(空中バレー)」である。
このアルバムも話題にならずニルソンが世間的に知名度を得るのは翌69年になるが、セールス的なことは置いておいて間違いなくこれが最高傑作だろう。前作同様のボーカルの多重録音、カメレオンボイス、スキャットが炸裂し、前作以上のソングライティングと緻密なアレンジ、そしてフレッド・ニール〝Everybody's Talkin'(うわさの男)〟の名カバー、文句なしの名盤。
続く!
勢いのまま書きたいが今回はここまで!次回はこの「空中バレー」から!
ひとまずモンキーズ辺りからソフトロック図に繋げときます↓

ソフトロック全体図↓

では!


